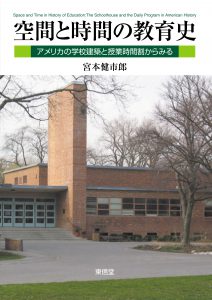【書評】宮本健市郎著『空間と時間の教育史 アメリカの学校建築と授業時間割から見る』
『教育学研究』第86巻 第1号 2019年3月
斉藤 仁一朗(東海大学)より
「隠れたカリキュラム」の研究では、授業者本人も意識できていない影響を実証的に明らかにする必要があり、非常に繊細な作業を要する。本書は、アメリカ教育史を通して、学校建築と時間割編成を視点としながら、学校における隠れたカリキュラムを解明することを試みている。本書は二部構成になっており、第一部では「学校空間の構成原理」について、第二部では「時間割の編成原理」についての詳しい考察が行われている。目次は以下の通りである。
はしがき
序 章 空間と時間の教育史へ
第一部:アメリカにおける学校空間の構成原理
第1章 進歩主義教育運動における学校建築思想の転換―教師中心の現場から子ども中心の学習環境へ
第2章 学校建築における講堂の出現と変貌
第3章 教育環境としての校舎の発見―アリス・バロウズの学校建築思想
第4章 工場モデルから家庭モデルへ―エンゲルハートの学校建築思想
第二部:アメリカにおける授業時間割の編成原理
第5章 コモン・スクール成立期の時間割―神の代理としての教師
第6章 工業化時代の時間割―管理の対象としての教師
第7章 新教育運動期における時間割の弾力化―教師の権威と専門性
終 章 新教育運動期における空間構成論と時間編成論の転換―子ども中心と教師の権威と専門性
付 章 日本における授業時間割編成原理の展開
まず、序章においては、本書が、19世紀末から20世紀前半の学校における空間構成と時間構成の二点に注目しながら、子ども中心の思想がどのように学校に反映されていたのかを明らかにする点が述べられている。その際に、学校建築と時間割に子ども中心の思想が現れる時期の違いにも注目を促している。
第1章では、主に学校建築の史的展開が示される。まず、19世紀には、教師中心の学校としての「教会モデル」の校舎が主流であった。その背景には教室の秩序の追求があり、教師は絶対的権威を持っていた。次に19世紀末~20世紀初頭に工業化・都市化などが進む中で、大規模校舎としての「工場モデル」の校舎が出現した。これは多くの子どもを収容できる効率性を追求した学校建築への移行であった。この頃から、ウィリアム・B・イトナーやアリス・バロウズらが子ども中心の校舎の誕生に向けて寄与したり、校舎のデザインに教育者が関わったことによって、20世紀前半において、「家庭モデル」の校舎が誕生したとされる。最後に、ウィネトカのクロウ・アイランド小学校が設立された経緯が紹介され、「クロウ・アイランド小学校の校舎が、『アメリカの学校建築史上の記念碑的作品』であることは間違いない」(p.41.)と先行研究の通説が再確認されている。
第2章では、「新教育の時代の校舎の変貌をもっともよく表している」(p.47.)とされる講堂の誕生に焦点が当てられている。19世紀半ばには、一教室学校であった学校の大教室が複数に分割され、学校に「ホール」登場した。さらに19末頃にはより意図を明確にした「集会場」も登場していく。その後、20世紀初頭には地域や社会生活をつなぐものとしての講堂の思想が普及していった。その後の20世紀半ばには、講堂から「多目的室」へと変化していき、講堂の考え方自体も、大きな講堂で子どもに緊張と不安を強いるのではなく、小さな講堂で子どもが積極的に参加することに主眼を置くようになったことが示されている。
第3章ではアリス・バロウズの学校建築思想が詳細に分析されている。バロウズは、デューイの出会い以降、デューイの教育理論を公立学校に応用することを目指して、独自の道を進んでいった人物である。バロウズは後に、ニューヨーク市へのゲーリー・プラン導入に尽力したが、他の関係者の導入意図がバロウズの意図とは異なり、経費削減に向けられていたという指摘が興味深い。その後、バロウズは教育環境の視点から「都市における子供の生活経験の貧困化」や「校舎の機能的計画」に注目するようになり、子どもの自由な活動や表現を保証するための校舎のありかたを追求していったことが示されている。
第4章では、エンゲルハートの学校建築思想が詳細に分析されている。エンゲルハートは校舎採点簿によって、学校建築研究の専門家としての地域を確立したとされる人物である。エンゲルハート自身が、進歩主義教育の思想に影響を受けながら、工場モデル校舎から家庭モデル校舎への変化を遂げた過程が、校舎採点簿の改訂内容と共に、示されている。また、エンゲルハートの思想の背景には、当時のモダニズム建築の影響がある点も指摘されている。
第5章では、コモン・スクールが成立する以前の時間割についての考察をなされている。19世紀前半は、決められた時間を厳守するのではなく、時間割の決め方も教師の裁量が大きかった。その背景には、「教師の権威は神に与えられたもの」(p.140.)という考え方があり、ゆえにその象徴が時間割だったことが述べられている。
第6章では、工業化時代の時間割について論じられている。資本主義の発展に伴い、公立学校にも能率性を追求する方針が見られ、時間割編成の議論が始まったとされる。次第にクラスが分けられ、学年ごとでの時間配分も決められるようになった。これらの時間割のシステムを教師が変更するのは容易ではなく、「教師の権威は、能率を追求する学校システムに吸収された」(p.165.)と述べられている。
第7章では、ゲーリー・プランを始め、幾つかの時間割の事例的検討をすることで、柔軟な時間割が出現した背景を追っている。ゲーリー・プランがそれ以前の科学的管理法と異なり、時間区分の基準が弾力化し、時間割作成への子どもの参加が可能になったと再評価されている。また、時間割改革が起こっていった過程として、プエブロ・プランやデューイ・スクール、ウィネトカ・プラン、ドルトン・プラン、リンカン・スクール、シティ・アンド・カントリー・スクールなどの進歩主義学校などの事例も検討されている。これらの事例では、学習者のリズムと自発性を保証すべきとされ、時間割の作成に子どもも参加していた。このような子どものリズムや主体性を保証するためには、専門家としての教師自身が時間割を作成することが必要であると指摘されている。
終章の主題は、「子ども中心と教師の権威と専門性」とされる。本書を総括し、「学校空間と時間割の柔軟性は相互に関連して、子ども中心の教育を支えていたとみることができる。このとき、教師には空間や時間をつくり上げる専門性が求められていたのである。」(p.208.)と結論付けられている。また、子ども中心の校舎をデザインする上で、教師もデザインに参加する必要があることが指摘されている。
付章では、日本において、45分という授業の単位時間が決まっていった過程が分析されている。学制成立当初は、時間割は各府県、各学校が自由に決めていたのに対して、明治後期になり、徐々に時間割表が全国一律になり、画一化が進んだことが示されている。その上で、遅くとも1890年代には、45分を授業の単位時間にする形式が休憩時間の考え方と併せて、普及していたとされる。大正新教育において、定式化した時間割に対して出された批判についても検討されている。
以上のように本書は、学校における空間と時間をめぐって、能率性の追求と教師の専門性との葛藤を描き出していると言える。
2.本書の意義
本書では、主に19世紀前半から20世紀前半の100年にわたるスパンを対象として論じられており、多くの写真や挿入史料が用いられている。そして、著者の広い視野と緻密な調査・分析の足跡を確認することができる。本書の意義を4点に絞って述べさせて頂く。
第一は、主体的で民主的な市民を育てるために、学習環境としてのデザインのモデルを示している点である。おそらく、民主的な市民を育てるためには、内容としての民主主義だけではなく、「場」としての民主主義も必要になってくる。本書で示された学校建築や時間割の事例は、まさにそのような民主的な場をデザインする試みである。このような点は、デューイの『学校と社会』で出てくる子どもたちの学びに合った机と椅子を買おうとするエピソードとも通じるし、今日のワークショップデザインなどの考え方とも通底している部分があるだろう。本書は、このような民主的な場づくりの重要性について、歴史的に明らかにした点に意義がある。
第二は、空間と時間をめぐって、「教師の専門性」への問い直しを促す点である。これは、本書の終章の主題ともなっており、子ども中心の学びを保証するには、建築と時間割の両方の専門的な理解をした上で、対応ができる教師が必要とされることになる。ただ、「工場モデル」が普及する中で、ある種の脱専門化された教師が、空間や時間をコントロールする力をどうすれば取り戻すことができるのだろうか。仮に、クロウ・アイランド小学校の例に学ぶとすれば、それは、教師自身が学校教育の前提を吟味し直すような、学習環境や子どもの成長を根本から考える姿勢であろう。仮に校舎だけ借りてきて他の教師が授業をしても、その空間をうまく活用できないと思われる。とするならば、教師には教室の学習環境をデザインする研究や、児童理解のための研究などがより一層となることが、本研究から示唆される。
第三は、カリキュラム研究として、施設・設備の質が、授業実践の質を左右することを再確認させてくれる点である。一般に、カリキュラムの理論研究では、こういった施設・設備の問題は周辺的な問題として軽視されがちである。しかし、本書を読むと、施設・設備の整備が理想とする授業像自体を規定していることが分かる。ただ一方で、著者自身も認めているように、特に新しい学校建築が実施できるかどうかという点は、単に理論的な問題にとどまらず、財政的な問題とも関連するであろう。第3章でプラツーン案が全国に普及したのもそれが理由の一つとされるが、このような点について、より掘り下げた分析も見てみたい。財源の確保が学校建築の可否に直結するのであれば、その資金を獲得する経緯自体もカリキュラム研究の射程に入ると言えるように思われる。空間と時間の問題は、単に教師の専門性だけの議論で解決することではない。
第四は、教科教育史の問い直しを促す点である。主に教科教育史を専門とする筆者にとって、学校建築や時間割の視点は、授業改革が学校改革として全教科が一体に進められることを実感させてくれる例とも見えた。時間割や学校建築の問題を突き詰めていけば、おのずと「教科は必要なのか?」というラディカルな問いにも繋がっていく。学校建築や時間割の視点は、教科教育史の前提自体を捉え直すことを促していると言える。
このように本書が教育研究に投げかける点は多岐にわたる。アメリカ教育史という特定分野のみに留まらず、学校教育の前提を問い直す上で、重要な著作であるといえる。
(東海大学 斉藤仁一朗)