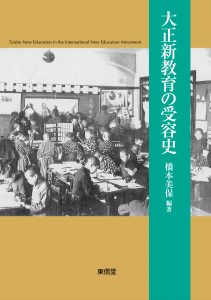『教育学研究』第86巻 第1号 2019年3月
本書の目的は、「国際新教育運動の中に大正新教育を位置づけることを視野に入れて、海外の新教育情報が日本の教育現場に受容されていくプロセスを解明し、それを通して教育実践の質的向上を支えた要因について考察すること」である。
本書は2部構成となっており、第1部では情報普及の全体状況を俯瞰し、第2部ではその俯瞰図の中に事例を位置づけつつ実態を解明する作業を行い、これらの事実を縦糸と横糸を織りなすように重ねて進めることによって、大正新教育の実像を浮き彫りにしていくことをねらっている。
第1部「欧米新教育情報と日本の教育会」では、日本の教育実践改革に影響を与えた海外の新教育情報が教育ジャーナリズムに取り上げられた状況を検討し、教育会への普及状況を明らかにした。第1章「モンテッソーリ教育情報の普及」(永井優美)では、モンテッソーリ教育情報が、批判論も含めて主としてアメリカ、イギリス経由で流入したものであったことを明らかにした。第2章「ゲーリー・プラン情報の普及」(角谷亮太郎・塚原健太)では、ゲーリー・プラン情報が、1913年以降、20年にわたって継続的に日本に紹介され、「効率的な学校経営」という点が一貫して報じられていたことを明らかにした。第3章「ドクロリー教育情報の普及」(橋本美保)では、ドクロリー教育法がヨーロッパの新教育運動に対する関心の高まりを背景として注目され始め、1920年代には主として実践家が、1930年代には理論家がこれを紹介していたことを明らかにした。第4章「プロジェクト・メソッド情報の普及」(遠座知恵)では、1920年代初頭に流行したプロジェクト・メソッドの日本における研究拠点と、そこでの理解の特徴を明らかにした。第5章「ドルトン・プラン情報の普及」(遠座・角谷)では、ロンドン・タイムズ教育版を通してドルトン・プラン情報の普及が始まり、パーカストによる全国各地の講演が関心のピークを生み出した点、同プランの意図が「学校の社会化」にあると理解されたことを明らかにした。第6章「ウィネトカ・プラン情報の普及」(宮野尚)では、ウィネトカ・プラン情報の普及の特徴を3期に区分し、ウォシュバーンの言説が同プランの情報源であっただけでなく、国際新教育運動との交流をとりもつメディアとして実践家たちに新教育理念の具現化プロセスを顕示する役割を担ったことを明らかにした。
第2部「国際的視点からのアプローチの可能性」では、海外の新教育情報が日本で研究され、教育現場に取り入れられた事例に注目し、実践家たちがどのような文脈で海外の情報を理解し、彼らの学校改革に結びつけていったのかを明らかにしている。第7章「北澤種一によるデモクラシー概念の受容」(遠座)では、作業教育の提唱者である北澤種一が、デューイのデモクラシー概念から「共通の興味」というアイディアを獲得し、それを核とする学級経営論を提唱していったことを明らかにした。第8章「甲賀ふじによる進歩主義保育実践の受容」(永井)では、戦前保育界の実質的な指導者である甲賀ふじが、シカゴ大学などでの留学経験を経て、豊明幼稚園において児童研究に基づく進歩的な実践に早期に着手したことを明らかにした。第9章「大正新教育におけるサティス・コールマン「創造的音楽」の受容」(塚原)では、コールマンの「創造的音楽」が受容主体の立場によって多様に理解されたことを明らかにした。第10章「明石女子師範学校付属小学校におけるドクロリー教育法の受容」(橋本)では、日本にカリキュラム理論を導入した及川平治が、デューイの教育論に重ねてドクロリーの生活教育論を理解し、子どもの必要と興味に沿った活動の組織化による「生活単位のカリキュラム」開発を提唱したことを明らかにした。第11章「大正新教育の実践に与えたドクロリー教育法の影響」(遠座・橋本)では、東京女校師附小と明石附小の訓導らの実践解釈や実践的営為の分析を通じて、ドクロリー教育法が両校の訓導たちに与えた思想的影響を明らかにした。
これまでの大正新教育研究では、そこで展開された多様な実践について、教育運動、教育方法、教育思想など様々な側面から検討がなされてきたが、とりわけ社会改革運動としての限界が強調されてきた。こうした研究動向に対して、編著者の橋本らは教育実践に内在する本質的価値に着目して大正新教育の思想史的意義を考察し、運動や実践に通底する「生命思想」の存在を明らかにした(橋本美保・田中智志編著『大正新教育の思想』東信堂、2015年)。本書では、前著の成果を受けて、大正新教育に影響を与えた諸思想の受容に焦点を当て、それらが教育メディアを通して受容された実態を整理・分析している。これまで個別に検討されてきた海外の新教育情報の伝達・受容プロセスの全体像を明らかにしたことが、本書の成果のひとつとして評価できるだろう。
本書の結論として、新教育情報の普及過程において、理論家(教育学者)が海外教育情報の最初の紹介窓口となる一方で、幅広い人材を含み厚い層をなした「実際家」たちによって新教育情報が研究され、様々な角度からの情報の活用が模索されていたことが指摘されている。学校現場にあった「実際家」たちすなわち受容主体としての実践家たちは、それぞれに明確な課題意識を持って新教育情報を求め、それぞれの文脈で情報を理解した。そして己が信じた価値を、教育・保育実践を通して実現する方とを考えるにあたって、海外で生成された情報を目の前の子どもたちの生動に応じて解釈し、それぞれの実践に応用するという形で受容した。本書では、こうした個別的で固有な営みこそが、大正新教育の豊かさを醸成していたと捉えている。
さらに、本書では実践史と思想史を架橋する「受容史」という方法的視角により、実践を支えてる教師の「生動」としての思想史に迫ろうとしている。体系的な思想や理論として残されることの少ない実践家の思想や信念を実践の中からつかみ出すには、彼らの言葉や行動を精査し、重ね合わせて、実践解釈や実践的営為を読み解く必要がある。本書では、実践主体の葛藤やその思想の構造化過程を解明するためには、編著者の橋本による『明治初期におけるアメリカ教育情報受容の研究』(風間書房、1998年)を発展させ、「受容史」という方法を採った。
教育思想の受容に焦点を当てるにあたって、本書では、従来、「知」と呼ばれていたものを「情報」と捉え直している。そして、「知」を「情報」と捉え直すことの方法上の利点として、「「知」の構造だけでなく、「知」とならずにこぼれ落ちたものや、変質した情報の存在を認識することができ、その意味を検討することが可能になる。情報受容のプロセスを解明することは、情報の需要や捨象の実態をも明らかにすることになる」と述べている。こうした視角の前提となっているのは、「知」が静的なものであるのに対して、「情報」は伝達・受容の過程で変容するものだという認識であろう。教育思想を「情報」と捉えてその変容に着目し、多くの媒体をくぐる過程で再解釈をくり返されながら受容されていく過程を明らかにした点、そして、そうした受容過程における媒介行為の重層性、共同性を明らかにしたという点もまた本書の成果として評価できる。
しかし、「受容史」という方法においては、教育思想を「知」として捉えることの積極的意義もあるのではないだろうか。著者らは、「大正新教育に関する従来の研究では「実践」に焦点を当てた分析が数多く行われてきたが、思想を顧みない実践史研究は、実践家の課題意識を看過する危険性を孕んでいる」(「思想史と実践史を架橋する―新教育研究への提案」『近代教育フォーラム』No.27、2018、p.118、遠座報告部分)という課題意識を持ち、実践史と思想史をつなぐ方法として「受容史」という方法を採用した。「知」は様々な情報をもとに反省的思惟によって深められ生成されるものと考えられるが、教育実践の根幹にある教師の「実践思想」もまた、同様の生成過程をたどる。教育思想を「情報」として捉え直すとともに、あえて「知」として位置づけ、その生成の局面についての検討もあわせて行われることで、「教育思想の受容史」をさらに深く豊かに描くことが可能になるのではないかと考える。
また、本書ではこうした情報の受容に際して重要な役割をになったのが教育の「実際家」であるとする。本書では、①アカデミックな研究者・理論家、②運動や実践のオルガナイザーとして実践をモデル化する立場にあった実践家、③個別の実践に関わる実践家、という三層構造で新教育の担い手を捉えている。そして②または③の立場にあり、新教育の「思想」を実践として「具現化」する「実際家」として、師範附小主事、新学校創設者、師範附小訓導らが取り上げられている。
しかし、新教育運動のオルガナイザーであった教師たちと、教室で日々の実践に携わった教師とでは、それぞれの「実践思想」の構築の背景や文脈、反省の質が異なるのではないだろうか。本書では「実際家」の言動から「内面の変化」を読み取り、その意味を明らかにしようとしているが、この「内面の変化」は、自らの行為(実践)に改造を迫る反省的実践家としての教師の性格を浮き彫りにしている。それぞれの「実際家」の立場や反省の質についてさらに精査した上で、彼らの「実践思想」形成および変容を検討する必要があるだろう。さらなる研究の進展を期待したい。
(和光大学 大西公恵)