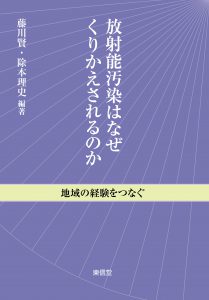藤川賢・除本理史編著『 放射能汚染はなぜくりかえされるのか』
佐賀新聞 6月9日より
低線量被ばくの健康リスクに関する科学的知見が確立していないにもかかわらず、市民に大丈夫だと説明することで、不安を解消しなくてはならないという一方通行型の「啓蒙主義」が横行していないか—
東京電力福島第1原発事故後、被害者の救済や賠償の問題を究明する大阪市立大の除本理史教授が、新編著放射能汚染はなぜくりかえされるのか」(東信堂)でこんな問いをしている。
事故から7年が経過したが、今も多くの「自主避難者」が福島県内外で暮らしている。強制的な避難エリアの外にもともと住んでいたが、被ばくリスクへの不安から、地元を離れた人たちだ。
政府は年間20ミリシーベルトの被ばく線量を目安に住民避難に関わる政策を決定してきた。その背景には、この値を国際放射線防護委員会(ICRP)などが定めた国際基準とみなす姿勢がある。
だが、20ミリシーベルトを下回わる低線量被ばくの健康リスクは完全排除できず、「グレーゾーン」との見方があるのも事実。昨年の前橋地裁判決も「20ミリシーベルトを下回る低線量被ばくによる健康被害を懸念することが科学出来に不適切であるということまではできない」としている。
因果関係や影響の度合いが必ずしも明確でない段階から、被害回復のための対策をあらかじめ講じるべきだという考え方が当然あっていい—。除本氏はこうも力説する。
この「予防原則」に立脚するなら、自主避難者らの抱く不安を、単なる主観や思い込みと片付けることは到底できない。それは充分に合理性のある不安だからだ。
中には、不安を口にすることが被災者間の対立や「風評被害」を招くと心配する人もいるだろう。しかし、そんな声なき声を無視する先にあるのは事故の風化である。
【東信堂 本体価格2,000円】