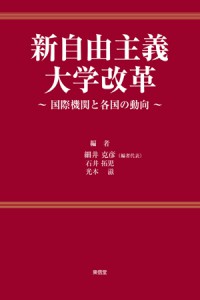【書評】細井克彦 編集代表『新自由大学主義改革』
経済 第二三一号 書評より (2014年12月1日発行)
6月に学校教育法と国立大学法人法が改正され、来年度から大学改革が加速することが決まった。昨年5月、教育再生実行会議が発表した第三次提言は、大学のガバナンス改革と経営基盤の強化をうたっていたが、これを法制化したかたちである。昨年10月の第四次提言ではグローバル人材の育成が強調され、今年7月の第五次提言では教育は未来への投資である、と断言された。新自由主義教育改革はますます加速しつつある。
このタイミングで大学改革の総合的研究とも呼ぶべき本書が上梓されたのは、大学改革の行方を考えるうえで時宜にかなっているというほかない。
本書の特徴の一つは国外の動向を把握するうえで、世界銀行(第2章)、OECD(第2・3章)、WTO(第8章)といった国際機関(本書ではグローバライザーと称している)の動向に注目していることである(第1部)。PISA(学習到達度調査)が有名になってOECD(経済協力開発機構)は教育界でも何かと言及されるようになったが、グローバリゼーションとはアメリカ一国によるものでもなく、OECDという一機構によるものでもなく、利害関係がうずまく諸国と国際経済を調整する諸機関が御膳立てする舞台回しのうえに成り立っていることを本書は教えてくれる。
また、外国の事例として、日本の大学教育改革モデルとされているアメリカ(第4章)や、イギリス(第5章)、ニュージーランド(第6章)のように新自由主義教育改革の典型例をとりあげるだけでなく、インドネシア(第7章)、ベトナム(第8章)、中国(第9章)、韓国(第10章)といった東南アジア・東アジア諸国の事例を取り上げていることも注目すべき点であろう。東南アジア・東アジアの改革をみることによって、国際機関が教育改革でいかなる役割を担っているかがあぶりだされるしかけとなっている。中国によるWTO加盟条件の実行が遅れた結果、続いたベトナムでは厳格な条件履行が迫られ、急速な新自由主義改革が迫られたといった国際的なダイナミズムは、一国単位での分析や単なる諸外国の事例の並列では明らかにならないであろう。その意味で、国外の動向を分析した第Ⅱ部は、各章が完結したものになっているだけでなく、ガバナンス改革に焦点をあてるという視点が一貫しているため、有機的に連動してまさしく国際動向の分析として機能している。
第Ⅲ部は、日本の改革動向に内在して、その普遍性と特殊性を浮かび上がらせるものである。
来年度から施行される国立大学改革は、教育内容・方法のグローバル化もさることながら、グローバルな大学間競争を勝ち抜くための組織づくりにテコ入れしている点に特徴がある。すなわち学長の権限強化を代表とするガバナンス改革である。本書では国立大学のみならず、公立、私立大学における改革動向をカバーし、大学改革の系譜を1980年代の臨教審・大学審答申にさかのぼる。そして現在の国立大学法人制度は、当初の法人化論から性格が変容していることを明らかにしている(第11章)。また、大学改革なるものが、行政改革や産業競争力強化といった教育外の動きによっていかに翻弄されたものであるかを分析してみせる(第12章)。本書はグローバル化の潮流を批判的に検討する視点を一貫させているが、初めに結論ありきといった平板な分析ではない。資本主義経済社会の維持・発展を目的として自由化を推進する市場派グローバリゼーション以外に、正義派グローバリゼーションと呼ぶべきものもあることを示したうえで、新自由主義を市場派グローバリゼーションの思想として位置づける(第1章)。そのうえで大学改革は、国外の潮流に流されるだけでなく、国内固有の要因と思惑によって推進される人為的なものでもあり、超国際的・国際的・国内的に重層的に展開されるものと位置づける。新自由主義の先進国と比べると約10年の遅れがあったものの、自治と民主主義の基盤が弱い中で歯止めがきかず、いまや新自由主義改革の先頭に立っている。これが、本書の示す日本の改革の国際的位置である。
終章では原子力政策と大学改革政策の同質性が論じられる。いささか唐突な感があったものの、科学的知見や構成員の意見が無視され、外部の意見を聞き、政治主導ですすめられることの問題点の指摘にはうなずけるところがあった、大学改革は高等教育政策という側面だけでなく、科学技術政策という側面ももっている。科学技術政策は高等教育政策以上に選択と集中が進んでいる領域だけに、原子力政策の轍を踏まないように、という警句は重い意味をもっている。目標管理が徹底され、自律性の確立が自己責任体制の確立へとすり替えられた結果、「知の共同体」から「知の企業体」へと組み替えられた、とする指摘は、大学関係者の多くが実感するところだろう。それは「学問の自由」に対する社会的認知が低下していることの裏返しでもある。本書は国内外の大学改革を総合的に扱った充実した書だが、ないものねだりをするならば、もう少し大学の自治に関する論述が多くてもよかったかもしれない(学問と自由の関係〔第12章〕、法人評価との関係〔第14章〕、教授会の合意形成機能〔第15章〕、そして終章における問題提起、と断片的には論じられている)。もっともこれは、そもそも大学の自治自体が議論されなくなっている状況の反映かもしれない。自己責任の原則のもと、各大学が〝自主的に〟学問の自由と自治を手放すようにならないためには、どうすればよいのか。
近年、高等教育で着手された改革モデルが高校、義務教育諸学校へと波及する傾向がみられる。大学に直接関係しない人々にもぜひ手に取っていただきたい。
(中田康彦 なかたやすひこ・一橋大学教授) twitter down
【東信堂 本体価格3,800円】