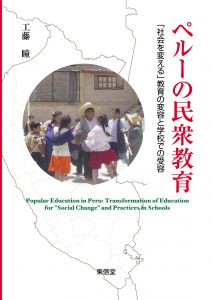【書評】工藤瞳著『ペルーの民衆教育―「社会を変える」教育の変容と学校での受容』
(A5・210頁・¥3200+税)
日本比較教育学会 比較教育学研究第58号 2019年
斉藤泰雄(国立教育政策研究所名誉所員)より
民衆教育(educación popular)という言葉は、ラテンアメリカの文脈で使用されるとき、その穏やかな語感とはうらはらに、特有の政治的意志とイデオロギー性をひそませた言葉であり概念である。それは、20世紀後半のラテンアメリカを代表する思想家であり社会運動家の一人であったブラジル人教育家パウロ・フレイレの思想や教育方法論を基盤としており、その理念に共鳴し、ラテンアメリカ各国・地域においてその実践をめざそうとする人々によって共有され、その活動を支える理念である。ラテンアメリカにおける厳然たる階級社会状況の存在を前提として、その底辺部にかれた被支配階級あるいは被抑圧者の意識覚醒と解放をめざす教育という意味あいを含んでいる。
その立場は、反体制・反政府的とまではいえないとしても、政府の教育政策とは一線を画し、抵抗や代替案を提示する教育運動論という性格を色濃く帯びたものである。著者自身も民衆教育を、「エリート主義的義的で既存の社会構造を温存する教育制度への批判として生まれたものであり、農民や都市周辺部の住民等の社会的に不利な状況にある人々が不平等な社会を批判的に捉え、社会を変革するための教育、その主体を育成するための教育」(4頁)と定義する。
1960年代から1980年代にかけて、民衆教育は、ラテンアメリカ発の、そしてラテンアメリカ的特色が濃厚な教育思想、教育運動論として地域内外の活動家や研究者の注目をあつめる存在であった。それゆえすぐれた先行研究も少なくない。フレイレ教育論の研究を含めればその数はさらに増す。それゆえに、若手研究者にとっては目の前に高い壁がたちはだかるような研究課題といえるかもしれない。本書は、このような民衆教育研究に果敢に取り組んだ著者によってもたらされた力作である。書名は、主な調査対象地域となったペルーに限定されているが、民衆教育の運動は、汎ラテンアメリカ規模の広がりを見せるものであり、著者の視点もラテンアメリカ地域全体を視野にいれたものである。
本書は次のように構成される。
序章
第一章 ラテンアメリカにおける民衆教育の形成
第二章 1990年代以降のラテンアメリカ民衆教育のパラダイム
第三章 ペルーにおける民衆教育と教育政策、市民社会
第四章 ペルーの共同体教育政策から見る民衆教育の限界
第五章 ペルーの働く子どもの運動マントックと民衆教育
第六章 ペルーでのカトリック系国際NGOフェ・イ・アレグリアの民衆教育
終章 民衆教育の現代的意味
第一章、第三章(第一節~三節)において、ラテンアメリカ全体、特にペルーにおいて民衆教育が、どのようにして登場してきたか、その特色はどのようなものであったか、という歴史的形成過程をたんねんに記述する。ここでは、1960年代から70年代にかけて、保守的な独裁政権や強権的な軍事政権がラテンアメリカ地域の多数の国を統治し、伝統的支配階層に属さない下層民集層への監視と統制を強め、住民の疎外感と閉塞感がつのるなか、民衆教育がそうした時代趨勢へのある種の抵抗運動として出現してきた経緯が語られる。これはラテンアメリカの現代教育史の流れを概観しながら、その中に民衆教育を位置づける作業となっており、先行研究や資料を博捜しながら要点をおさえた簡明な整理となっている。
しかしながら、本書の独自性はここからである。伝統的ラテンアメリカの社会構造は、1980年代にこの地域をおそった深刻な経済危機を転機として大きな変貌をとげることになる。すなわち、軍事政権や長期独裁政権の退潮による政治的民主化の進展、新自由主義政策の浸透と構造改革、グローバル経済への参入、安定成長の持続と市民社会の成熟、社会正義の希求や人権意識高揚、国際世論や国際潮流への積極的対応などの現象である。
地域全体として、90年代に入ると、教育にたいする国民の関心が一段と高まり、より積極的に教育改革を求める声が大きくなる。最近の教育改革論議に見られる新しい傾向の一つとして、グローバル化や国際競争を意識してか、欧米や日本のような先進国の教育水準のみならず、経済成長の著しいアジアの国々の教育状況が引き合いに出されるようなケースも目につく。教育の質の問題が意識されるにしたがって、この地域では従来ほとんど注目されることのなかった生徒の学業成績の国際比較調査にも関心が高まっていった。こうした変化は、民衆教育にも影響をあたえるものであり。民衆教育もまた変容をせまられた。
ラテンアメリカの研究者のなかにも、民衆教育は、ラテンアメリカ社会の変貌のなかで、その歴史的使命を終え、いわば一世を風靡したひとつの歴史的な概念、歴史的遺産となっていると見なす者も少なくない。あるいは、その理念は、抵抗の論理という性格を弱め、各国政府の教育政策のなかに組み入れられて主流化するというかたちで発展的に解消したとみなす見かたもある。はたして現実はどうであるのか。著者の関心は、この点に焦点づけられており、いうなれば「あの民衆教育のその後の姿」を見きわめようとする意欲的なものである。この鮮明な課題意識が本書に、ある種の力動観と独自性を与えるものとなっている。
ここからの研究は、あまり文献研究に依存することができなくなるため、著者は、ペルー一国に対象を絞り込み、民衆教育の正当な継承者を主張する団体、民衆教育とは袂を分かったとする団体、民衆教育論が盛んだった時代にはまだ本格的に登場していなかった各種のNGO組織、民衆教育の陣営から中央・地方の教育政策担当者・教育行政官に転身した人物など多彩な関係者に面談調査を重ね、さらにはウェブサイトの調査を併用し、そこに民衆教育の理念やエトスの存在の有無、またその濃淡をさぐるという手法を多用することとなる。いずれも、体力、気力、忍耐力を求められる作業であるが、その努力の成果は本書において確かに結実しているといえよう。ちなみに、本書は、著者が2016年に京都大学に提出して授与された博士論文が基礎となっている。
民衆教育の変容の様相としては、著者は、(1)先住民・ジェンダー・市民権・人権・理念の教育制度内部への取り込みと包摂、(3)学校教育への接近を確認する(171-173頁)。確かに、民衆教育から「尖った」̚カドはとれ、その輪郭は鮮明さを失ってきたといえよう。しかし、著者は、本書の最後尾において、その将来像にふれて、もし仮に将来変容がそこまで発展したなら、民衆教育はもはやその命脈をとどめなくなるという条件を想定する。それは、(1)個人の幸福や利益、社会的上昇だけを目標とした教育となる、(2)既存の教育制度に対する批判的機能を失った場合、(3)学習者の関心や日常生活からかけ離れた内容が学習の中心となった場合(178頁)、という。逆にここまで事態が変化しないかぎり、「より公正で民主主義的に『社会を変える』ことを求める教育思想や実践は、それを民衆教育と呼ぶか否か、学校教育の外で行うか否かに関わらず、今後も受け継がれていくであろう」と結論する。著者は、民衆教育にたいして直接的にシンパシーを表明することはなく、またその変容に対して個人的な見解や批評を明示することも慎重にひかえている。しかし、この最後の言葉には、評者もおおいに共感するところである。
最後にひとつだけ細墐をあげるなら、第五章「働く子どもの運動MANTHOC」に関する部分である。世界的に児童労働禁止の世論が高まるなか、あえてそれに抗するように、子ども・若者が働くことを肯定的にとらえ、独自の活動を展開するNGOを紹介する。これ自体、開発途上国いおける児童労働論議として興味深いものではあるが、民衆教育の継承と変容という本書の全体構成の脈絡においては、やや据わりが悪いという印象は否めない。本書の一章として組み入れる際に、運動の主唱者クシアノビッチとフレイレとの人脈関係、かれ自身のフレイレ論など民衆教育へのアンビバレントな感情にもう少し踏み込んだ言及があってもよかったのではないかという思いは残る。