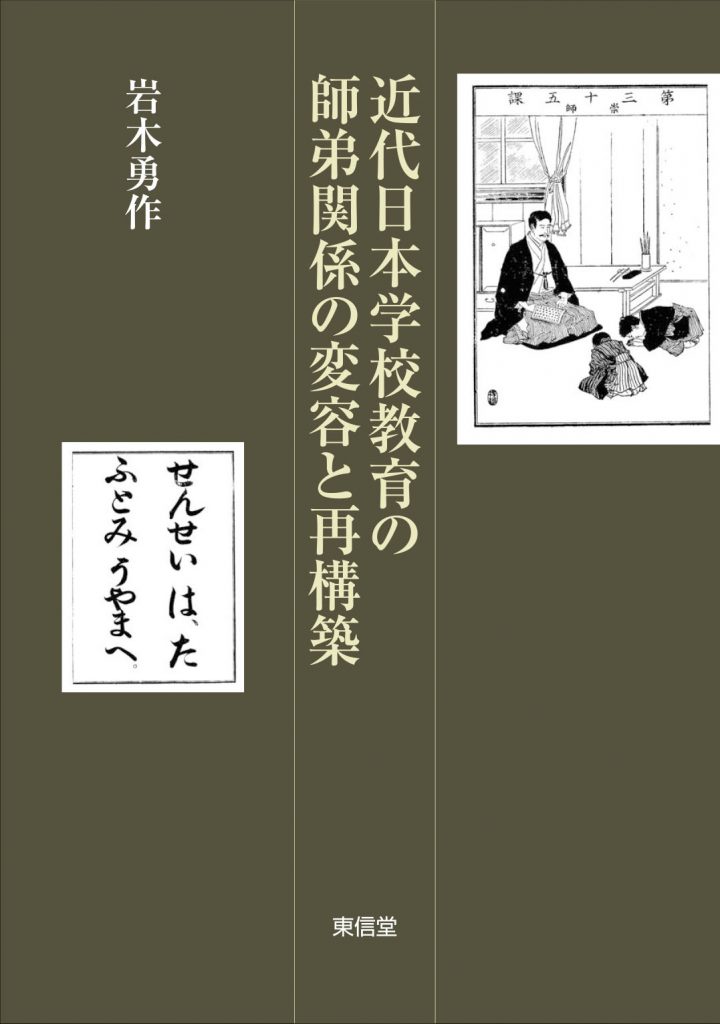『近代日本学校教育の師弟関係の変容と再構築』
(四六判、312頁、3700+税)
山田恵吾(埼玉大学)より
本書を貫く問いは、「教員はなぜ『尊敬』されなければならないのか」である。著者の岩木勇作氏は、研究のきっかけについて、教育実習生が「先生」と呼ばれること(『尊敬』されること)に対する「違和感」があったという。「教員」とは如何なる存在なのか、教育の「関係」とは何なのか。近世から近代への教育的関係の変容を辿ることによって、現代の学校教育の問題性を浮かび上がらせる。この課題を歴史研究へと昇華させたのが本書である。2018年3月に学位授与された博士論文がもとになっている。
現在(2020年8月)、多くの大学でオンライン授業を実施している状況下、あらためて学校の役割、教師の役割について考えさせられる機会は多い。ほぼすべての学生がスマートフォンを身に付け、知りたいことがあれば、大概のことはネットに接続すれば事足りる。オンデマンドの講義も画像に表示される情報に過ぎない。「知」の在りかとしての価値が低下している学校・教師に、それでもなお欠かせない役割とは何か。本書の問いは、その存在意義に関わる極めて現代的なものである。
本書の構成は次の通りである。
序章 学校教育における師弟関係とは何か
第1章 個人教育と学校教育―「校長」と「教員」の登場―
第2章 学校教育における「教権」概念と呼称―教員と一体化する教権―
第3章 明治期の学校紛擾と「校風」―師弟関係の一つの帰着点―
第4章 橘蔭学館における学校革命―学校紛擾の裏面―
第5章 近代学校教育における「校訓」―教育勅語以前・以後―
終章 近代学校教育制度化においてなぜ師弟関係は必要とされたか
第1章では、1学級・1教員からなる単級学校と複数の学級・教員からなる多級学校との比較を通じて、それぞれの特質を検討している。単級学校は寺子屋教育がモデルとなるもので、「教育組織の統一が容易であり、かつ学校の理想的な統一である家族的統一が行われうる」ものである。これに対して多級学校は、家族的統一、教育組織の統一に欠けており、教育的関係に変容をもたらす。この欠点の補正が重要な課題となることを指摘した。
第2章では、明治期の教権確立論の分析を通して「教権」概念を検討している。教権の確立が教員を「主」、生徒を「従」とするような関係づくりを意味し、当時主流であった単級学校における教育の良否を左右するものとされていた点を明らかにした。また、生徒に対する呼び捨て・敬称可否論に注目している。「呼称」問題が、教員の人格に依存する教育的関係の不安定を背景に現れ、教育上の権威保持のための「実質を伴わない擬制師弟関係(親子関係に類似した親しさを理想とする)」を要請するものであったことを指摘した。
第3章では、明治20年代の中等教育機関における学校紛擾に「師道頽廃」の認識が共通して存在することを『教育時論』の分析を通じて明らかにしている。「徳」から「学」へと重点を移す「師道」の変容、頻繁な教員の異動状況などから、教員個人に求められていた「師道」からの脱却が迫られ、新しい教権として学校の「校風」が注目されるようになったことを指摘した。
第4章では、明治24年福岡県橘蔭学館で起きた学校紛擾の中心人物である藤村作に注目し、生徒側からからみた学校紛擾の論理と「『青年』的実践」のありようを検討し、その「学校革命」としての側面を明らかにしている。
第5章では明治20年代から40年代の小学校における「校訓」の役割について検討している。明治20年代以降に多級学校が増加すると、それまで単級学校において維持されていた師弟関係に似た家族的関係の維持が困難となり、「校訓」制定によって多級学校に家族的関係を定着させようとしたことを指摘した。
総じて、近世の「徳」を身に付けた師への尊敬により成立していた教育的関係=「師弟関係」が、近代学校教育の学級編制の変化に即して変容した点を明らかにした。師への尊敬は「教権」を維持するための手段となり、やがて多級学校の普及に伴って、より安定した教育的関係を促すものとして「家族関係」が期待される。「校訓」「校風」は、近代学校教育を「家族関係」によって安定させるものとして登場したということになる。そして、これらの検討結果を踏まえて、岩木氏は現代における教育的関係のあり方について次のように述べる。すなわち、「学校教育内において、師弟関係が形成されることは現代においては不適切ですらあるだろう。そもそも近代学校教育に師弟の全人格的な関係を求めることは無茶の類である」。だから、現在の学校教育においては「教育目的、方法、内容によって最もよい関係が追究されるべき」であり、「常にオルタナティブな関係が可能性として存在することを認識」し、「関係の選択、態度の選択が、教育方法論中に取り入れられることが望ましい」と。
子どもが新しい経験をし、学ぼうとする動機はどこにあるのか。辻本雅史氏『「学び」の復権―模倣と習熟―』(岩波文庫)は、意味がわからなくても繰り返し暗誦して身体に憶えさせる、江戸時代の「滲み込み型」の学習を可能としたのは良い大人の存在・師との出会いであるという。役に立ちそうもない、憶えたり理解するのが面倒なことに向かって、子どもに「跳躍」させるのが大人の振る舞いであり、教師の存在意義ということになる。本書は、そのような学びへと子どもを「跳躍」させる何かについて問うものでもある。これまで日本教育史において、教育史は養成史・研修史を中心に多くの蓄積がある一方で、教員と児童(生徒)との関係そのものを問う研究となるとそれほど多くの蓄積があるわけではない。「尊敬」をキーワードに、単級学校・多級学校という学校・学級編制の変化が及ぼした教師と児童(生徒)の関係の変化を指摘し、教育的関係の歴史を切り拓こうとした本書の学術的な意義は大きい。
本書からたくさんのことを学び、刺激を受けた一方でいくつか疑問が浮かんでくる。
江戸時代の師弟関係が、近代学校の出現に伴って、とりわけ単級学校から多級学校の普及によって危機を迎え、その対応として「校訓」「校風」による家族的学校観が登場するという理路は明快である。しかしながら、師弟関係の変化は、はたして単級学校から多級学校という変数のみで説明しきれるものなのだろうか。
岩木氏本書の研究方法について、構築主義的アプローチをとることを強調している。「関係」の事実(「実態」)よりも認識(「言説」)を重視するというのである。しかしながら、「言説」といってもそれがどういう事実についてのものか、それなりに限定しなければ、観念の歴史になってしまう。単級学校から多級学校という教師と子どもを取り巻く教育環境の現実を教育的関係の前提していること、加えて地域差の大きい、多様な明治初期の実態を扱うのであればなおのこと、事実をおさえなければ「言説」の解釈に説得力を得るのは難しい。
たとえば、変数としての地域(共同体)と家庭と学校の三者の関係性はどうだろうか。単級学校の時代は就学率は低く、学校の価値を理解する家庭の子弟こそが就学していたであろうから、教師と児童の私的な教育的関係を望む地域や家庭も一定数はいただろう。一方、学校の価値を理解しない、むしろ反感を持つ人々の多かった地域では学校を「打ち毀し」、教育的関係そのものが学校には存在しなかった。就学への抵抗と促進の力学も働く。教育への理解度、学校の価値の拡がりといった変数も「師弟関係」の変容に影響するのではないか。「校訓」「校風」の登場に関しても地域と家庭の「学校」認識に即して捉えれば、その意図も的確に捉えることができる。他にも小学校の進級試験や教員の属性なども気になる。いずれにしても、明治初期の地域と学校の多様な実態とその変化に即して「教育的関係」を捉える必要があるのではないか、というのが一点目の疑問である。
二点目は、初等教育と中等教育の「教育的関係」同列に扱っている点である。第1章、第2章では、近世から明治期の教育的関係の変容を、寺子屋師匠・寺子の関係から単級・多級学校の教師・児童の関係において捉えている。ここまでは「変容」を見る窓口は初等教育の学級編制で一貫している。しかし、第3章では中学校と師範学校の教師・生徒の関係となり、第4章では私立学校の「青年」の学校観を中心に、中等教育の学校紛擾に焦点が絞られる。第5章では再び小学校を舞台に多級学校における「校訓」を「変容」への対応(「再構築」)として捉える。つまり、第1章、第2章、第5章では初等教育のシステムへの対応として教育的関係の変化を、第3章、第4章では中等教育の学校紛擾における教育的関係を捉えているのである。岩木氏は初等教育と中等教育に共通する変容であると位置づけているようであるが、初等教育と中等教育では教師のあり方も教育内容も児童(生徒)も異なる。とりわけ当時の中等学校はエリート校である。それぞれの特質に応じた教育的関係を構造的に明らかにできれば、面白いと思う。
そして、岩木氏が提唱する選択可能な教育的関係についてである。「師弟」「家族」という教育的関係の虚構性を結論づけたのであるから、現在の学校教育の形を前提とした、可変的な教育的関係の模索ではなく(それもまた虚構)、学校教育の形そのものを揺さぶる方向で考えた方が自然ではないか。たとえ虚構であっても、「教員」「児童」という役があればこそ、数十人、数百人の子どもが登場する「学校」というドラマが成り立っているからである。
最後に、「教員」の呼称をてがかりに教員像の変容に取り組んだ「先人」の研究に触れておきたい。前近代から近代への移行期において、教職者に対する呼称を反映した教育的関係とその変化の過程を明らかにした、宮坂朋幸氏の研究がある。(「教職者の呼称の変化に表れた教職者像に関する研究―明治初期筑摩県伊那地方を事例として―」日本教育史研究会『日本教育史研究』第22号、2003年)。宮坂氏は、政府が「教職者」に込めた期待に加えて、住民が「教職者」に込めた期待を地域の実態に即して検討しており、近世から近代における「師弟関係」の変容に言及している。「教職者」像は当然のことながら教育的関係に関わる問題であり、本書の重要な先行研究となりうるものである。本書では言及されなかったが、こうした研究成果をどうとらえるのか知りたいところであった。
あらためて、本書は教育の本丸ともいえる問いに、正面から取り組んだ意欲的な成果である。今後の研究の展開を楽しみにしている。
(日本教育学会編『教育学研究87号』掲載)