【書評】寺崎昌男著 『大学自らの総合カⅡ 大学再生への構想力』
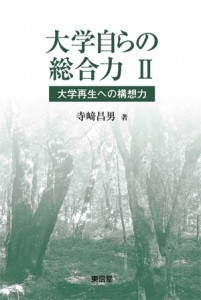
この本の著者の寺崎昌男さんの講演なら、何度でも聴きたいと思っている人 が多い。評者もその一人である。さりげないご自身の経験談から始まって、ごく簡素なレジュメに沿って話が進んで行く。大学史研究者としての該博な知識とご自身の体験とを踏まえて、問題の歴史的背景から本質まで、明快に、ゆっくりと、聞きようによっては訥々と、しかし自在に議論して、最後に聴衆に深い感銘を与える。 ご自身の言葉を借りれば、「彼らは実は安培したのです。満足ではなく『安諸感」です。」と述べている。これはかつて勤務しておられた大学で行った自校史の講義を回想的に述べたときの言葉だが、著者の話を聞くために集まった聴衆の反応一般について言えることだと思う。
本書は、主として2010年から2014年にかけて行われた講演やシンポジウムの発題の原稿をもとに編集されたもので、一読して、著者の肉声が聞こえてくるような 臨場感あふれる内容になっている。
第I部「基本の問題から」では、まず1990年代に立教大学で取り組んだ「全学共通カリキュラム」という教養カリキュラムを新たに編成したときの体験をもとに、カリキュラムとは何か、学士課程とは何か、教養とは何かという大学教育の基本となる問題を論じている。それに、大学と地域の関係を論じた大阪市立大学での講演、大学職員の能力開発 (SD) についてわが国で初めて本格的に論じた論文及び校友・同窓会と大学の関係を分析した論文の4つでこの部が成り立っている。 著者が大学教育の課題に立ち向かうときの原理・原則の多くがここで述べられている。
大学教育とくに教養教育について印象的ないくつかの言葉が見出される。いずれも至言だと思う。「リベラル・アーツて何ですか?」と質問されるたびに、「言葉自体は、歴史用語だと思います」と答えていたが、やがて、「現代におけるリベラル・アーツとはすなわち、現代において世界を見る目だ」と気づく。このようにして、現代的リベラル・アーツのカリキュラムづくりの手掛かりを得ていく。
また、地域への貢献について悩む大学について、「これを克服していく道は、やはり学問や教育の質における勝負しかないだろう」と述べる。例えば、大阪なら、「大阪市を背景とした学問の創造がなければならない。この創造が学生、出身者、市民を通じて大阪の文化、経済、社会生活の真髄となって行く時に、大学が市民生活の内に織り込まれて設立の意義を全くする」。
第Ⅱ部はこの数年ご自身が率先して活動して来た自校教育とアーカイブスに関する3つの論考をまとめたもので、大学史研究者としての著者の面目が躍如としている。自校教育の良いところは、演説やアピールではなくて、「講義」の形式をとることだという (第2章)。すなわち、「何が真実であり、何が真実でないかあるいは、真実と思われる事柄の中からこれを話すのか、話さないのか、この辺の判断を決めるのは講演者自身」で、これはドイツの大学で形成された「教授の自由」の原則にほかならないという。
第Ⅲ部では、大学の授業と教育そのものの改革を具体的に扱った論考を取り上げている。その中の、海外の大学院指導論に関するマニュアルを解説した第2章で、学生と指導教員の組み合わせが完璧なケースなどほとんど存在しない、双方とも「私はこの人物と基本的な関係を築けるか?」と自問しながら持続可能な関係を目指して自問していく必要がある。というくだりが印象的だった。
冒頭にもどって、なぜ著者の講演は集まった人々に安塔感を与えるだろうか?
お人柄にもよるが、基本は講演者と聴衆とが「当事者意識」を共有しているからだと思う。著者は大学にかかわるさまざまな問題を「教育学」のデイシプリンで切って見せるようなことはしない。そもそも「教育学部は課題から生まれた学部であって、ディシプリンから生まれた学部ではなかった」という認識が著者にはある。その延長として、学部の後ろ盾を持たないセンターの責任者になって、5つの「部局」と対峙しなら「大学は専門性に立つ教養人をつくる」という目標のもとにカリキュラムを構築して行く過程が述べられている。まさに「課題解決型ディシプリン」の本領発揮である。「全学を通じての公共的ニーズに即する」ことだけを理論的な武器に悪戦苦闘する著者の姿は、聴衆の共感を呼び、人々を励ましそして安心させる。
さらに印象的なのは、大学と大学を構成する人々、および学生すべてに注がれる。著者の広い関心と深い愛情だろう。第Ⅱ部で、真実が何かという視点から見た大学は、歴史から見ると「人間の愚行というものを端的に示す場所」でもある。 しかし、明らかにすべきは、さまざまな時点における各大学の「選択の歴史」で ある。それを一つ一つ明らかにしていくと、その大学の体質というか理念が浮かび挙がってくる。従って、建学の精神は 「実態の変化に応じて深化・再生し、ときに変わりうるもの」である。それを知った学生は自分の居場所がわかり、その先生がどんな人かということもわかる。だから「安心」する。こうして、学生は自分の大学に関心を持つようになり、参加の意識が育ち、やがて生涯の故郷として、またいつでも立ち寄る泉としての大学を持つようになる。このような学生の成長に対する関心こそ「教育学」のすべてだ、ということは評者のような門外漢にも理解できることである。
小笠原 正明 (一般社团法人大学教育学会会畏· 北海道大学名誉教授/物理化学 評)
【束信堂 本体価格2,400円】













